
アイダ設計の980万の家という魅力的な価格の住宅プランに、多くの方が関心を寄せていることでしょう。
しかし、その一方で「本当に980万円で家が建つのか」「何か裏があるのではないか」といった不安や疑問を感じるのも自然なことだと思います。
この記事では、アイダ設計の980万の家を検討しているあなたが抱えるであろう、総費用や間取り、評判、そして考えられるデメリットに関するあらゆる疑問に答えていきます。
住宅の購入は、一生に一度の大きな買い物であり、後悔だけは絶対にしたくないものです。
だからこそ、価格に含まれる標準の仕様や、どこまでがオプションで追加費用となるのかを正確に把握することが重要になります。
また、規格住宅としてのメリットやデメリット、坪単価の考え方についても詳しく解説し、あなたが納得して家づくりを進められるようサポートします。
実際に家を建てた人の評判や口コミを参考にしながら、後悔しないためのポイントを一緒に確認していきましょう。
- ➤アイダ設計の980万の家の価格に含まれる標準仕様
- ➤どこまでが追加費用となるオプション工事なのか
- ➤間取りの自由度と規格住宅としての制約
- ➤最終的に必要となるリアルな総費用の目安
- ➤購入前に知っておくべきデメリットや評判
- ➤低価格を実現している坪単価の仕組み
- ➤後悔しないために比較検討すべきポイント
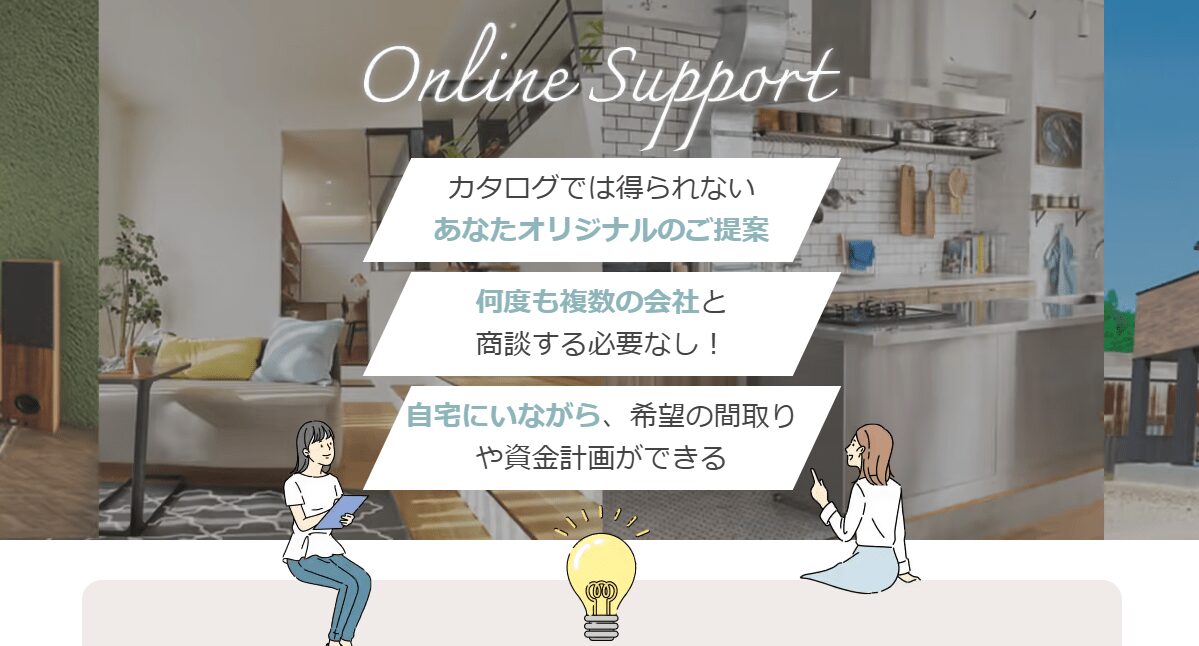
| 【タウンライフ❖家づくり】 | |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 見積り | あり |
| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |
| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |
| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |
「タウンライフ家づくり」は、サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から提案を受けることができるサービスです。
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。
大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。
アイダ設計の980万の家は本当にその価格で建つのか
- ➤980万円に含まれる標準仕様と設備
- ➤自由設計はどこまで可能?間取りの範囲
- ➤別途必要となる追加費用とオプション工事
- ➤最終的にかかる費用の総額シミュレーション
- ➤なぜこの価格が実現できる?坪単価の秘密
980万円に含まれる標準仕様と設備

アイダ設計の980万の家が注目される最大の理由は、その驚異的な価格設定にあります。
しかし、多くの方が疑問に思うのは「その価格で、一体どこまでの設備や仕様が含まれているのか」という点でしょう。
結論から言うと、980万円という価格には、日常生活を送る上で必要最低限の基本的な構造体と設備が含まれています。
これはいわゆる「本体価格」と呼ばれるものであり、家そのものの価値を示すものです。
具体的に、どのようなものが標準仕様として設定されているのか見ていきましょう。
まず、建物の基礎や構造躯体、屋根、外壁、窓といった、家の骨格を形成する部分は当然含まれています。
これらがなければ家として成り立たないため、基本中の基本と言えるでしょう。
内装に関しては、壁紙(クロス)やフローリング、室内ドアといった基本的な仕上げも標準仕様の範囲内です。
ただし、選べる種類や色には制限がある場合がほとんどで、特定のカタログから選択する形式が一般的です。
水回り設備についても、システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレといった設備は一式含まれています。
これらも生活に不可欠な設備ですが、メーカーやグレードは指定されたものの中から選ぶことになり、高機能なものやデザイン性の高いものを選ぶ場合はオプションとなります。
例えば、キッチンの食洗機や浴室の暖房乾燥機などは、多くの場合オプション扱いとなることを理解しておく必要があります。
また、給湯器や基本的な照明器具、コンセント、スイッチ類も標準で設置されます。
ただし、これも各部屋に最低限必要な数が設置されるという考え方であり、生活スタイルに合わせて数を増やしたり、特殊な照明を取り付けたりする場合は追加費用が発生します。
重要なのは、この980万円という価格が、あくまで「建物本体」の価格であるという点です。
土地代はもちろんのこと、後述する付帯工事費や諸経費は一切含まれていません。
そのため、「980万円さえあれば家が手に入る」と考えるのは早計であり、この標準仕様の内容を正確に理解した上で、自身の理想の暮らしと照らし合わせ、どこにオプション費用をかけるべきかを検討していくことが、賢い家づくりの第一歩となるのです。
自由設計はどこまで可能?間取りの範囲
アイダ設計の980万の家は、「規格住宅」というカテゴリに分類されます。
この「規格住宅」という言葉が、間取りの自由度を理解する上で非常に重要なキーワードとなります。
規格住宅とは、あらかじめ用意されたいくつかの基本プラン(間取り)の中から、自分のライフスタイルや土地の形状に合ったものを選んで建てるスタイルの住宅です。
これにより、設計のプロセスが大幅に簡略化され、コストを抑えることが可能になっています。
では、アイダ設計の980万の家では、自由設計の余地は全くないのでしょうか。
答えは「限定的な範囲で可能」です。
完全にゼロから自由に設計する「フルオーダー住宅」とは異なりますが、用意された基本プランをベースに、ある程度のカスタマイズが認められています。
例えば、壁の位置を少しずらして部屋の広さを調整したり、収納(クローゼット)の位置を変更したりといった軽微な変更は、対応してもらえる可能性があります。
また、部屋の用途を変更する、例えば「和室を洋室にする」といった変更も、構造上の問題がなければ可能な範囲です。
しかし、建物の外形や大きさ、窓の位置や数、階段の場所といった、家の構造に関わる根本的な部分の変更は基本的に難しいと考えた方が良いでしょう。
これらの要素は、建築確認申請や構造計算に大きく影響するため、変更するには多大なコストと時間がかかってしまい、規格住宅のメリットが失われてしまうからです。
間取りの選択肢は、数十種類以上用意されていることが多く、延床面積や部屋数、階数(平屋か2階建てか)など、様々なバリエーションの中から選ぶことができます。
そのため、多くの人にとって、その中から自分の理想に近いプランを見つけることは十分に可能でしょう。
重要なのは、自分の理想の暮らしを具体的にイメージし、用意されたプランの中で、そのイメージに最も近いものはどれかを見極めることです。
そして、どうしても譲れない部分については、カスタマイズが可能かどうかを事前に担当者へ確認することが不可欠です。
「規格住宅」の範囲内で、いかに自分たちの暮らしにフィットさせていくかという視点が、アイダ設計の980万の家で満足のいく間取りを実現するための鍵となります。
別途必要となる追加費用とオプション工事
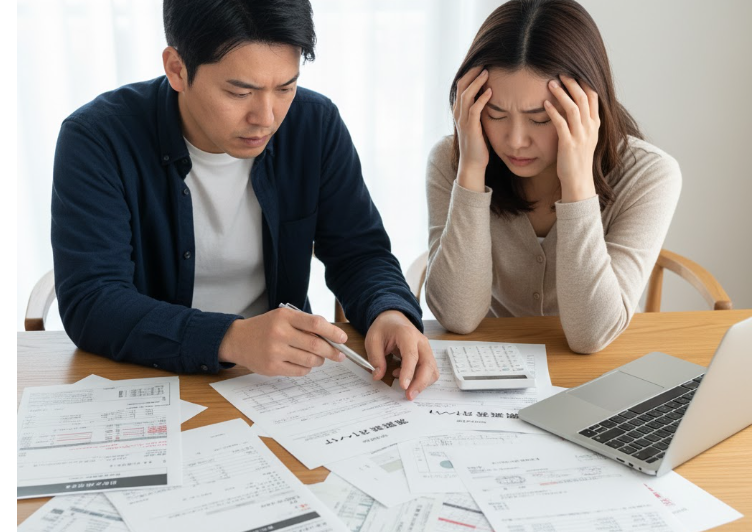
アイダ設計の980万の家を建てる際、最も注意しなければならないのが「本体価格以外にかかる費用」です。
前述の通り、980万円はあくまで建物本体の価格であり、実際に家を建てて住み始めるまでには、様々な追加費用やオプション工事費が必要となります。
これらを把握しておかないと、最終的な総額が予想を大幅に超えてしまい、資金計画が破綻してしまう可能性も否定できません。
まず、必ず必要となるのが「付帯工事費」です。
これは、建物を建てるために必須となる工事費用のことで、主に以下のようなものが含まれます。
- 地盤調査・改良工事費:土地の強度を調査し、必要であれば補強する費用。
- 給排水・ガス引き込み工事費:道路から敷地内へ水道管やガス管を引き込む費用。
- 屋外電気工事費:電柱から建物へ電気を引き込む費用。
- 仮設工事費:工事中の仮設トイレや水道、電気などの費用。
- 外構工事費:駐車場や門、フェンス、庭などを整備する費用。
これらの付帯工事費は、土地の状況やインフラの整備状況によって大きく変動しますが、一般的に150万円から300万円程度は見ておく必要があるでしょう。
次に「オプション工事費」です。
これは、標準仕様からグレードアップしたり、追加の設備を設置したりするための費用です。
例えば、以下のような項目が挙げられます。
- 内装・設備のグレードアップ(キッチン、バス、壁紙など)
- 収納の追加(カップボード、パントリー、ウォークインクローゼットなど)
- 窓の性能向上や追加(ペアガラスからトリプルガラスへ、シャッターの設置など)
- 照明器具やカーテンレールの設置
- 太陽光発電システムや蓄電池の設置
- 床暖房の設置
これらのオプションは、こだわり始めると際限なく費用が膨らんでいく部分です。
どこにこだわり、どこは標準仕様で満足するのか、事前に家族で優先順位を決めておくことが非常に重要です。
最後に、建物や工事以外にかかる「諸経費」も忘れてはなりません。
これには、建築確認申請手数料、登記費用(土地・建物の所有権移転など)、火災保険料、地震保険料、住宅ローンを組む際の手数料や保証料、そして不動産取得税や固定資産税といった税金が含まれます。
これらの諸経費も、合計で100万円から200万円程度は必要になると考えておきましょう。
このように、アイダ設計の980万の家を建てるためには、本体価格以外に様々な費用がかかることを、計画の初期段階でしっかりと認識しておくことが後悔しないための絶対条件です。
最終的にかかる費用の総額シミュレーション
では、アイダ設計の980万の家を建てる場合、最終的な総額は一体いくらくらいになるのでしょうか。
もちろん、土地の条件や選択するオプションによって大きく異なりますが、ここでは一つのモデルケースとして具体的なシミュレーションをしてみましょう。
まず、基本となる建物本体価格が980万円です。
費用の内訳
次に、前述した付帯工事費を計算します。
土地の地盤が比較的良好で、大規模な改良工事が不要だったと仮定し、給排水や電気の引き込みなども標準的な工事で済んだとして、付帯工事費を200万円と設定します。
この中には、最低限の外構工事(砂利敷きの駐車場など)も含まれるとします。
続いて、オプション工事費です。
ここでは、あまり贅沢はしないものの、生活の質を少し上げるための現実的なオプションを選択してみましょう。
- リビングのエアコン1台設置:15万円
- 全室のカーテンレールと基本的なカーテン設置:20万円
- 基本的な照明器具を全室に設置:15万円
- キッチンのカップボード(食器棚)設置:20万円
- 2階の1部屋にクローゼットを追加:10万円
これらのオプション工事費を合計すると80万円になります。
最後に、諸経費です。
住宅ローンの手数料、登記費用、各種保険料、税金などを合わせて150万円と見積もります。
それでは、これらの費用を合計してみましょう。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 建物本体価格 | 980万円 |
| 付帯工事費 | 200万円 |
| オプション工事費 | 80万円 |
| 諸経費 | 150万円 |
| 合計 | 1,410万円 |
このシミュレーション結果からわかるように、アイダ設計の980万の家を建てるための総額は、最低でも1,400万円から1,500万円程度になる可能性が高いということです。
もちろん、これはあくまで一例です。
地盤改良に100万円以上かかったり、外構工事にこだわってカーポートやウッドデッキを設置したりすれば、費用はさらに増加します。
逆に、エアコンやカーテンを自分で別途購入して設置するなど、工夫次第で費用を抑えることも可能です。
この総額シミュレーションは、アイダ設計の980万の家を検討する上での一つの目安として捉え、必ず自身の希望や土地の条件に合わせて、詳細な見積もりをハウスメーカーに依頼することが重要です。
「980万円」という数字だけに目を奪われず、総額でいくらかかるのかを常に意識して計画を進めましょう。
なぜこの価格が実現できる?坪単価の秘密

アイダ設計の980万の家が、なぜこれほどまでの低価格を実現できるのか、その仕組みに疑問を持つ方も多いでしょう。
その秘密を解き明かす鍵は、「坪単価」の考え方と、徹底したコストダウンの工夫にあります。
まず、住宅の価格を示す指標としてよく使われる「坪単価」ですが、これには明確な定義がなく、ハウスメーカーによって計算に含める項目が異なります。
一般的に、坪単価は「建物の本体価格 ÷ 延床面積(坪)」で計算されます。
アイダ設計の980万の家が、仮に延床面積30坪だとすると、坪単価は980万円 ÷ 30坪 = 約32.7万円となります。
これは、大手ハウスメーカーの坪単価が70万円以上であることを考えると、破格の安さであることがわかります。
この低価格を実現できる理由は、大きく分けて以下の4つのポイントが挙げられます。
1. 規格化による設計・開発コストの削減
前述の通り、アイダ設計の980万の家は規格住宅です。
あらかじめ決められたプランから選ぶことで、一棟ごとに設計士が図面を作成する手間とコストを大幅に削減しています。
これにより、設計料を安く抑えることができるのです。
2. 建材・設備の一括大量仕入れ
使用する建材やキッチン、バスなどの設備を特定のメーカーの特定の商品に絞り込み、全国の支店で一括して大量に仕入れることで、仕入れコストを劇的に下げています。
スケールメリットを最大限に活かした、ローコスト住宅ならではの戦略と言えるでしょう。
3. 施工プロセスの効率化
間取りや仕様がある程度決まっているため、職人の作業手順もマニュアル化しやすく、現場での施工プロセスを効率化できます。
無駄な作業をなくし、工期を短縮することで、人件費を削減することにつながります。
4. 広告宣伝費の抑制
テレビCMなどの大規模な広告を控え、住宅展示場への出展も最小限に抑えるなど、広告宣伝費を徹底的にカットしています。</
その分を、住宅の価格に還元しているのです。
これらの企業努力によって、驚異的な低価格が実現されています。
ただし、注意点として、この坪単価には付帯工事費や諸経費が含まれていないことを改めて認識しておく必要があります。
全ての費用を含めた「総額」を延床面積で割った実質的な坪単価は、当然ながらもっと高くなります。
アイダ設計の980万の家は、決して安かろう悪かろうというわけではなく、様々な工夫と合理化によって成り立っている商品であることを理解することが大切です。

| 【タウンライフ❖家づくり】 新しい住まいのプランを一括お届けサービス | |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 見積り | あり |
| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |
| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |
| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |
全国1,170社以上(※)の注文住宅会社を自宅にいながらまとめて比較できる「タウンライフ家づくり」。
サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から選べます。
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。
大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。

アイダ設計の980万の家で後悔しないための注意点
- ➤購入前に知るべきデメリットと評判
- ➤「規格住宅」であることの利点と欠点
- ➤耐久性は大丈夫?メンテナンスの実態
- ➤実際に建てた人のリアルな口コミ
- ➤アイダ設計の980万の家がおすすめな人
購入前に知るべきデメリットと評判

アイダ設計の980万の家は、価格面で非常に大きなメリットがある一方で、購入してから後悔しないためには、事前に知っておくべきデメリットや、世間一般の評判についても目を向ける必要があります。
価格が安いということは、何かしらの制約やトレードオフがあるのが一般的です。
まず、最大のデメリットとして挙げられるのが「標準仕様のシンプルさ」です。
980万円という価格に含まれる設備や建材は、あくまで基本的なグレードのものです。
最新の機能や高いデザイン性を求めると、そのほとんどがオプションとなり、追加費用が発生します。
そのため、標準仕様のままで満足できるかどうかが、コストを抑える上での大きな分かれ道となります。
展示場などで見た華やかなモデルハウスの仕様を基準に考えてしまうと、標準仕様とのギャップにがっかりしてしまう可能性があるため注意が必要です。
次に、間取りの自由度が低いという点もデメリットと感じる人がいるでしょう。
規格住宅であるため、フルオーダーのように自分のこだわりを細部まで反映させることは困難です。
「どうしてもこの場所に書斎が欲しい」「吹き抜けのある開放的なリビングにしたい」といった強いこだわりがある場合、規格プランの中では実現が難しいかもしれません。
また、評判に目を向けると、ポジティブな意見とネガティブな意見の両方が見られます。
ポジティブな評判としては、「この価格で新築一戸建てが持てて満足」「コストパフォーマンスは最高」といった、やはり価格に関する満足度の高さが目立ちます。
一方で、ネガティブな評判として散見されるのが「営業担当者の対応が良くなかった」「アフターサービスに不安がある」といった、品質そのものよりもスタッフの対応に関する声です。
これは、ローコストメーカーが多くの案件を抱え、一人当たりの担当業務が多くなりがちなことに起因する可能性があります。
もちろん、これは担当者個人の資質にもよるため一概には言えませんが、契約を急かされたり、質問への回答が曖昧だったりした場合は、慎重に検討する必要があるでしょう。
これらのデメリットや評判を総合すると、アイダ設計の980万の家は「住宅に強いこだわりはなく、基本的な性能の家をできるだけ安く手に入れたい」というニーズには非常にマッチする一方で、「細部までこだわった理想の家を建てたい」「手厚いサポートを期待したい」という人には、物足りなさを感じる可能性があると言えます。
メリットとデメリットを天秤にかけ、自分たちの価値観に合っているかどうかを見極めることが、後悔しないための最も重要なポイントです。
「規格住宅」であることの利点と欠点
アイダ設計の980万の家を理解する上で、改めて「規格住宅」の特性について深く掘り下げてみましょう。
規格住宅であることには、明確な利点(メリット)と欠点(デメリット)が存在します。
これらを正しく理解することで、自分たちの家づくりに最適な選択なのかを判断する材料になります。
規格住宅の利点(メリット)
- 価格が安い:最大のメリットは、何と言っても価格の安さです。設計の合理化や建材の大量仕入れにより、フルオーダーの注文住宅に比べて大幅にコストを抑えることができます。
- 完成イメージが湧きやすい:あらかじめ用意されたプランやモデルハウスがあるため、建てる前に家の完成形を具体的にイメージしやすいです。間取り図だけでは分かりにくい生活動線や広さの感覚を掴みやすいでしょう。
- 品質が安定している:仕様や工法がある程度マニュアル化されているため、職人の技術力による品質のばらつきが少なくなります。安定した品質の住宅を期待できる点は安心材料です。
- 工期が短い:設計プロセスが短く、施工手順も効率化されているため、契約から引き渡しまでの期間が比較的短い傾向にあります。早く新しい家に住みたいという方には大きなメリットです。
規格住宅の欠点(デメリット)
- 間取りの自由度が低い:これが最大のデメリットです。基本プランからの大幅な変更は難しく、自分のライフスタイルやこだわりに100%合致させることは困難な場合があります。
- デザインの画一性:似たようなプランが多いため、外観や内装のデザインが画一的になりがちです。「自分だけの個性的な家を建てたい」という方には物足りないかもしれません。
- 土地の形状に合わせにくい:規格プランは、基本的に整形地(四角形の土地)を想定して作られています。変形地や狭小地など、特殊な形状の土地にはプランがうまくはまらず、建築自体が難しい場合があります。
- 仕様・設備の選択肢が少ない:標準で選べる壁紙や床材、キッチンなどのメーカーや種類が限られています。こだわりの設備を導入したい場合は、オプションとして高額になるか、そもそも対応できない可能性があります。
このように、規格住宅はコストパフォーマンスと品質の安定性、工期の短さという大きな利点がある一方で、自由度や個性という面では制約を受けます。
アイダ設計の980万の家を検討する際には、自分たちが家づくりにおいて何を最も重視するのかを明確にすることが重要です。
「コストを最優先し、ある程度の制約は受け入れる」というスタンスであれば、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
しかし、「間取りやデザインに徹底的にこだわりたい」というのであれば、他の選択肢も視野に入れる必要があるかもしれません。
耐久性は大丈夫?メンテナンスの実態

「価格が安い家は、耐久性が低く、すぐに傷んでしまうのではないか」という不安を抱くのは、当然のことです。
特に、アイダ設計の980万の家のようなローコスト住宅を検討する場合、その構造的な強度や長期的な耐久性は非常に気になるポイントでしょう。
結論から言うと、現在の日本の建築基準法は非常に厳しく、アイダ設計の家も当然ながらその基準をクリアして建てられています。
法律で定められた耐震性や耐久性を満たしていない住宅は、そもそも建築許可が下りません。
そのため、「安かろう悪かろう」で、すぐに倒壊するような危険な家であるということはあり得ません。
アイダ設計では、日本の気候風土に適した木造軸組工法を基本としており、耐震性を高めるための工夫も随所に施されています。
例えば、建物の揺れを抑える耐力面材を使用したり、基礎と土台を強固に連結する金物を採用したりと、見えない部分でもしっかりと構造計算に基づいた設計がなされています。
ただし、耐久性を長期的に維持するためには、適切なメンテナンスが不可欠であるという点は、高価格な住宅もローコスト住宅も同じです。
特に、ローコスト住宅の場合、使用されている建材が標準的なグレードのものであることが多いため、メンテナンスの重要性はより高まると言えるかもしれません。
具体的に、どのようなメンテナンスが必要になるのでしょうか。
定期的に必要となる主なメンテナンス
- 外壁・屋根の再塗装(10年~15年周期):外壁材や屋根材そのものを保護している塗膜が紫外線などで劣化するため、定期的な再塗装が必要です。これを怠ると、雨漏りや構造材の腐食につながる可能性があります。
- シーリングの打ち替え(7年~10年周期):外壁材の継ぎ目を埋めているシーリング材は、ゴムのような素材でできているため、経年で硬化しひび割れてきます。ここからの浸水も大きな問題となるため、定期的な打ち替えが重要です。
- バルコニーの防水工事(10年~15年周期):バルコニーの床面には防水処理が施されていますが、これも永久的なものではありません。防水層の劣化は、階下への雨漏りの直接的な原因となります。
- 給湯器などの設備交換(10年~15年周期):給湯器や換気扇などの住宅設備には寿命があります。故障してから慌てないよう、10年を過ぎたあたりから交換を検討する必要があります。
これらのメンテナンス費用は、工事の内容にもよりますが、一度に数十万円から百万円以上かかることもあります。
家を建てた後も、こうした将来のメンテナンス費用を計画的に積み立てておくことが、家の耐久性を保ち、長く快適に住み続けるための秘訣です。
アイダ設計の980万の家を選ぶ際には、引き渡し後の保証制度やアフターサービスの内容についてもしっかりと確認し、長期的な視点で住まいの維持を考えていくことが大切です。
実際に建てた人のリアルな口コミ
アイダ設計の980万の家を検討する上で、何よりも参考になるのが、実際にその家を建てて住んでいる人たちの生の声、つまり「口コミ」です。
ここでは、インターネットやSNSなどで見られる良い口コミと悪い口コミを両方紹介し、多角的な視点からアイダ設計の家を評価してみましょう。
良い口コミ・評判
良い口コミとして最も多く見られるのは、やはりコストパフォーマンスに関するものです。
- 「同じ予算で考えていた中古マンションよりも、広くて新しい一戸建てが手に入って大満足です。賃貸の家賃を払い続けるのが馬鹿らしくなりました。」
- 「標準仕様でも十分生活できます。オプションをいくつか付けましたが、それでも他のハウスメーカーより圧倒的に安く済みました。」
- 「間取りの選択肢が思ったより多く、自分たちの生活スタイルに合ったプランが見つかりました。規格住宅でも不満はありません。」
- 「若い世代でも無理なくマイホームが持てる価格設定は本当にありがたい。営業担当の方も親身に相談に乗ってくれました。」
これらの口コミからは、特に予算に限りがある中で新築一戸建てを希望する層から、高い支持を得ていることがうかがえます。
基本的な性能を備えた住まいを、手の届く価格で提供している点が、最大の魅力として評価されているようです。
悪い口コミ・評判
一方で、もちろん悪い口コミも存在します。これらは、契約前や建築中、そして入居後の対応に関するものが多い傾向にあります。
- 「契約までは熱心だったのに、契約後は営業担当者との連絡がつきにくくなった。質問への返答も遅く、少し不安になった。」
- 「建築現場の整理整頓がされていなかった。職人さんの質にもばらつきがあるように感じた。」
- 「入居後にクロスの剥がれが見つかったが、アフターサービスの対応が遅い。こちらから何度も連絡して、ようやく修理に来てくれた。」
- 「標準仕様の建材が思ったより安っぽく感じた。モデルハウスとのギャップがあり、もう少しオプションを付ければよかったと後悔している。」
これらの口コミは、ローコストメーカー全般に共通して見られる課題とも言えます。
多くの案件を抱える中で、一人ひとりの顧客への対応が手薄になったり、下請けの職人の管理が行き届かなかったりするケースがあるのかもしれません。
また、価格が安い分、使用される建材のグレードもそれ相応であるため、品質に対する期待値が高すぎると、がっかりしてしまう可能性も示唆しています。
これらのリアルな口コミを踏まえると、アイダ設計の980万の家を成功させるためには、価格というメリットだけに目を向けるのではなく、担当者との相性を見極め、建築中もこまめに現場に足を運んで自分の目で確認し、引き渡し前には専門家による内覧会(ホームインスペクション)を依頼するなど、施主側にもある程度の知識と主体的な行動が求められると言えるでしょう。
アイダ設計の980万の家がおすすめな人

これまで、アイダ設計の980万の家に関する様々な情報、メリット・デメリットを詳しく見てきました。
これらの情報を総合的に判断すると、この住宅プランは、ある特定の人にとっては非常に魅力的で賢い選択肢となり得ますが、一方で、別の人にとっては後悔の原因にもなりかねません。
最後に、この記事のまとめとして、アイダ設計の980万の家がどのような人におすすめできるのか、その人物像を具体的に描いてみましょう。
まず、最もおすすめできるのは「コストを最優先に考え、できるだけ安く新築一戸建てを手に入れたい」という明確な目的を持っている人です。
特に、20代や30代の若い世代で、現在の家賃と同程度の支払いでマイホームを実現したいと考えている方々にとっては、まさに最適なプランと言えるでしょう。
中古住宅には抵抗があり、かつ注文住宅ほどの予算はない、という層のニーズに見事に応えています。
次に、「住宅に対する強いこだわりが少なく、シンプルな機能とデザインで満足できる」という人も、このプランに向いています。
「家は雨風がしのげて、快適に眠れれば十分」という価値観の方であれば、標準仕様のままでも大きな不満を感じることは少ないはずです。
むしろ、オプションを厳選することであらゆる無駄を削ぎ落とし、ミニマルで合理的な暮らしを実現できるかもしれません。
また、「ある程度、住宅に関する知識があり、主体的に家づくりに関わっていける」という人にもおすすめです。
担当者任せにせず、自分で仕様を確認したり、建築現場をチェックしたりすることで、トラブルを未然に防ぎ、満足度を高めることができます。
一方で、おすすめできないのは、細部にわたるデザインや間取りに強いこだわりがある人、あるいは住宅に高いステータス性や高級感を求める人です。
そのようなニーズに応えるためには、やはりそれ相応の費用と自由度が必要となります。
最終的に、家づくりで大切なのは、自分たちの予算と価値観に合った住宅会社を選ぶことです。
アイダ設計の980万の家が自分たちに合っていると感じたとしても、即決するのは禁物です。
理想の家を建てるためには、複数の注文住宅会社から相見積もりを取り、提案内容や担当者の対応を比較検討することが、後悔しないための最も確実な方法と言えるでしょう。
- ➤アイダ設計の980万の家は建物本体の価格である
- ➤総費用は付帯工事費や諸経費を含め1400万円以上が目安
- ➤標準仕様は生活に最低限必要な設備が含まれる
- ➤こだわりを反映するにはオプション費用が追加で発生する
- ➤間取りは規格住宅のため自由度に制限がある
- ➤低価格は建材の一括仕入れや設計の合理化で実現
- ➤価格の安さが最大のメリットであり評判も高い
- ➤デメリットは仕様のシンプルさと自由度の低さ
- ➤耐久性は建築基準法をクリアしており問題ない
- ➤長期的な維持には定期的なメンテナンスが不可欠
- ➤口コミは価格への満足度と担当者の対応への指摘に分かれる
- ➤コストを最優先する人には非常におすすめできる
- ➤家づくりに強いこだわりがある人には不向きな場合もある
- ➤最終的な判断は複数の住宅会社との比較が重要
- ➤相見積もりで自分に合ったプランを見つけることが後悔しない秘訣
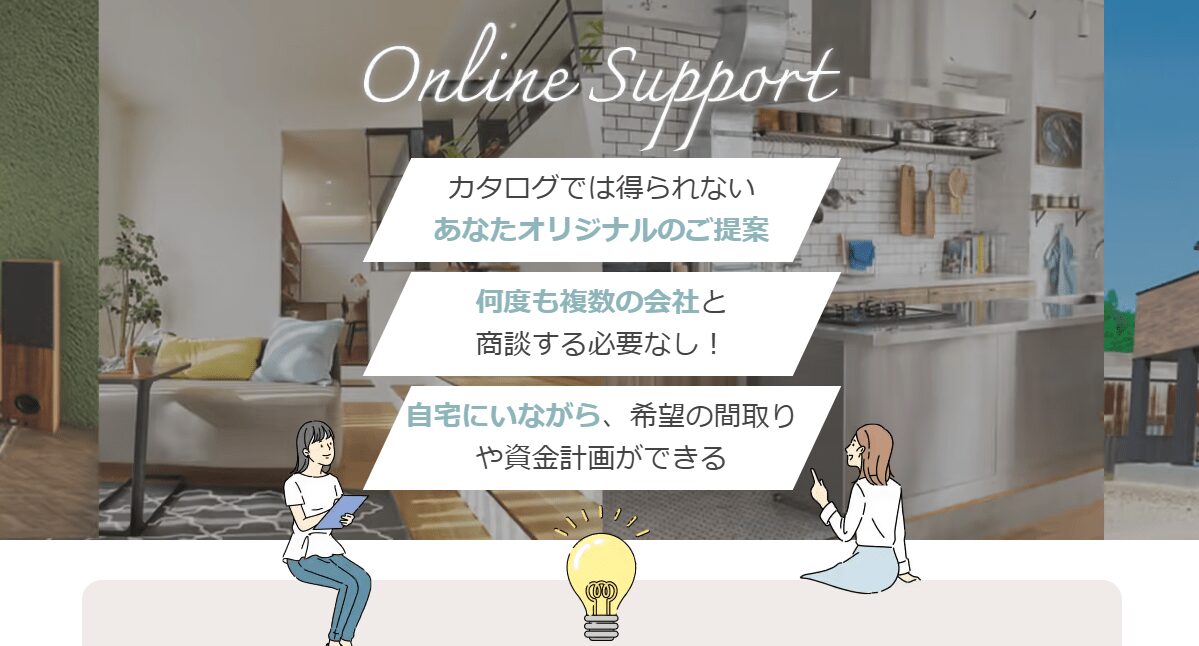
| 【タウンライフ❖家づくり】 | |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 見積り | あり |
| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |
| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |
| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |
「タウンライフ家づくり」は、サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から提案を受けることができるサービスです。
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。
大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。










