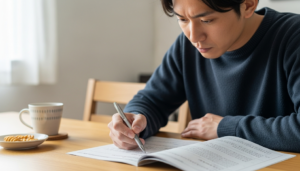「えっ、シロアリ予防だけで20万円…?」
積水ハウスで家を建てて10年目。
ようやく住宅ローンの返済にも慣れてきた頃にやってくるのが、カスタマーズセンターからの「10年点検」のお知らせです。
そこで渡される見積書を見て、思わず二度見してしまったという方は、決してあなただけではありません。
私も家づくりに関しては徹底的に調べるタイプですが、この「メンテナンス費用」に関しては、正直なところ「高いな」と感じる瞬間があります。
特に防蟻処理(シロアリ対策)は、目に見えない部分への投資だけに、その妥当性が分かりにくいものです。
「鉄骨住宅だからシロアリなんて関係ないのでは?」
「ネットで探した業者なら半額でできるのに、なぜ積水ハウスに頼まないといけないの?」
そんな疑問を持つのは当然のことです。
しかし、詳しく調査を進めると、ここには単なる「シロアリ駆除」以上の、非常にシビアな「保証のルール」が隠されていることが分かりました。
この記事では、リサーチャーとして集めたデータに基づき、防蟻処理の費用相場から、他社に依頼した場合の致命的なリスクまでを包み隠さず解説します。
後悔のない選択をするための、判断材料としてお役立てください。
- 積水ハウスの防蟻処理の費用相場は15〜20万円
- 防蟻処理は「構造躯体保証」の延長条件になっている
- 鉄骨住宅でも木部があるためシロアリ対策は必須
- 他社で施工すると積水ハウスの保証が打ち切られる
- バルコニー防水とセットで行うのが一般的
- 30年保証の「初期保証」適用物件なら条件が異なる
- 最終的に「安心料」として割り切れるかが判断の鍵
積水ハウス防蟻処理とは?保証延長と更新時期
- 積水ハウスの10年点検と防蟻処理の関係
- 薬剤の効果切れと再施工のタイミング
- 防蟻処理をしないと保証はどうなる?
まずは、なぜ10年目に防蟻処理が必要になるのか、その仕組みを整理しましょう。
多くのオーナー様が誤解されている部分ですが、これは単に「薬を撒く」だけの話ではありません。
積水ハウスという巨大な組織が提供する「長期保証システム」を維持するための、いわば「更新手続き」のような側面があるのです。
積水ハウスの10年点検と防蟻処理の関係

積水ハウスでは、引き渡しから10年が経過すると、無償の定期点検が行われます。
このタイミングが、家づくりにおける最初の大きな分岐点です。
新築時に約束されていた「初期保証(10年)」が満了を迎えるため、ここで何もしなければ、建物に対する重要な保証が終わってしまうのです。
積水ハウスの場合、保証を延長するための条件として「有償メンテナンス工事」が義務付けられています。
その必須項目の一つが、この「防蟻処理」なのです。
つまり、シロアリがいるかいないかに関わらず、「保証を継続したければ、指定の工事を受けてください」というのがメーカー側のスタンスなんですね。
これは、自動車の車検制度に少し似ています。
車が壊れていなくても、乗り続けるためには検査と整備にお金を払わなければならない。
それと同じで、積水ハウスの「安心」を乗り続けるためのコストだと理解するのが一番分かりやすいでしょう。
薬剤の効果切れと再施工のタイミング
「でも、新築の時にしっかり薬を撒いているはずでしょう?」と思われるかもしれません。
確かにその通りです。
しかし、現在日本の住宅で使用されている防蟻薬剤は、環境や人体への影響を考慮して、効果が5年から10年程度で切れるように作られています。
昔の薬剤のように、一度撒けば半永久的に効くような強い毒性のあるものは、今は使えないのです。
そのため、日本シロアリ対策協会などの基準でも、5年ごとの再施工が推奨されています。
積水ハウスの場合は、新築時の施工品質が高いため「10年」という期間設定になっていますが、それでも10年が限界なのです。
10年を過ぎると、床下のバリア効果が薄れ、シロアリが無防備に侵入できる状態になってしまいます。
防蟻処理をしないと保証はどうなる?
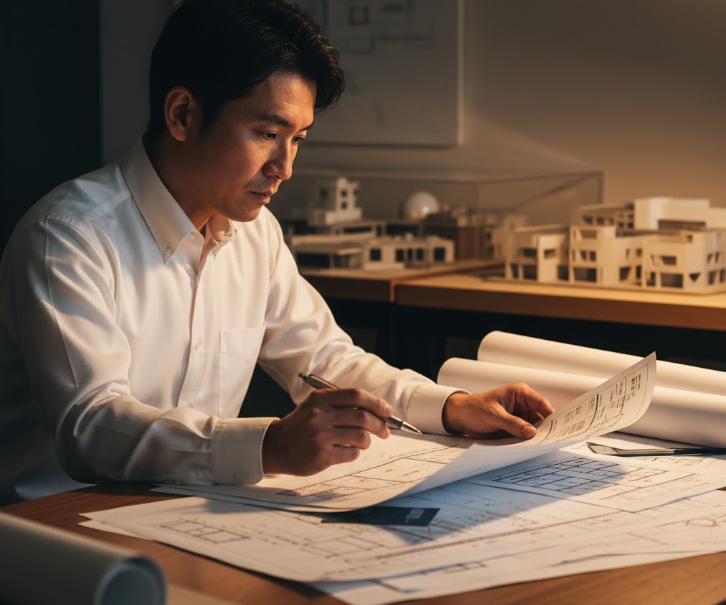
ここが最も重要なポイントです。
もし、10年目の点検で提案された防蟻処理(および必要な有償工事)を断った場合、どうなるのでしょうか。
結論から言うと、「構造躯体」と「雨水の侵入を防止する部分」の保証が、その時点で終了します。
- 基礎や柱などの「家の骨格」に関する保証がなくなる
- 雨漏りが発生しても、すべて自己負担での修理になる
- 将来売却する際、「メーカー保証なし」の物件として査定される可能性がある
シロアリの工事を断っただけなのに、雨漏りや柱の保証までなくなるというのは、少し理不尽に感じるかもしれません。
しかし、積水ハウスの理屈としては「シロアリ被害で構造が弱くなれば、地震で倒壊するリスクも高まる。だから防蟻処理をしない家の構造保証はできない」ということなのです。
非常に厳しいルールですが、これが積水ハウスの「ユートラスシステム(保証延長制度)」の現実です。
単なる「虫除け」ではなく、「家の保険の更新料」として捉える視点が必要です。
積水ハウスの防蟻処理の費用は?10年目の真実
- 30坪での防蟻処理費用の相場と坪単価
- バルコニー防水など他工事とのセット価格
- 積水ハウスの見積もりが高い理由と内訳
では、実際にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
私が独自に調査したオーナー様の口コミや、公開されている見積もりデータを集計し、リアルな相場を算出しました。
「高い」と言われますが、具体的な数字を知ることで、心の準備ができるはずです。
30坪での防蟻処理費用の相場と坪単価
積水ハウスのカスタマーズセンターから提示される防蟻処理の費用は、建物の大きさ(1階の床面積)によって決まります。
一般的な30坪〜35坪程度の戸建て住宅の場合、以下のような金額が目安となります。
- 延床面積30坪前後:約15万円〜20万円(税抜)
- 坪単価換算:約5,000円〜8,000円/坪
これはあくまで「防蟻処理単体」の価格です。
一般的なシロアリ駆除業者の相場が、坪あたり3,000円〜5,000円程度であることを考えると、やはり割高感は否めません。
積水ハウスの価格設定は、市場相場の約1.5倍から2倍近くに設定されているケースが多いようです。
この差額を「安心料」として許容できるかが、最初のハードルになります。
バルコニー防水など他工事とのセット価格
さらに注意が必要なのは、10年目のメンテナンスは防蟻処理だけでは終わらないことが多いという点です。
多くの場合、「バルコニーの防水シートのトップコート塗り替え」もセットで提案されます。
これも保証延長の必須条件に含まれていることが多いためです。
これらを合計すると、請求額は一気に跳ね上がります。
- 防蟻処理:約15万円
- バルコニー防水トップコート:約10万円〜15万円
- 合計:約25万円〜30万円(税抜)
「10年点検はお金がかからないと思っていたのに、いきなり30万円の出費!?」と驚かれるオーナー様が多いのは、このセット提案があるからなんですね。
積立や事前の資金計画をしていないと、家計に大きなダメージを与える金額です。
積水ハウスの見積もりが高い理由と内訳

なぜ、積水ハウスの見積もりはこれほど高いのでしょうか。
単に利益を乗せているだけ、と考えるのは簡単ですが、リサーチャーとして分析すると、いくつかの合理的な理由も見えてきます。
まず、積水ハウスの防蟻処理は、単に床下に潜って薬を撒くだけではありません。
配管周りの隙間を埋める処理や、基礎のひび割れチェックなど、積水ハウス独自の点検基準に基づいた作業が含まれています。
また、万が一シロアリ被害が発生した場合の「保証対応」のコストも、この金額に含まれています。
いわば、保険料込みの価格設定なのです。
そして何より大きいのが、「積水ハウスブランドの維持費」です。
下請け業者が実作業を行うにしても、積水ハウスの看板を背負って作業をする以上、トラブルがあればメーカーが責任を負います。
その管理コストや安心感が、価格に上乗せされていると考えるのが自然でしょう。
積水ハウスの防蟻処理は必要?鉄骨と木造の違い
- 鉄骨住宅でも防蟻処理が必要な理由
- シャーウッド(木造)のリスクと対策
- シロアリ被害に遭いやすい家の特徴
「うちはイズ・ロイエ(鉄骨)だから、シロアリなんて関係ないでしょ?」
そう思っている方は、少し危険かもしれません。
確かに鉄骨はシロアリに食べられませんが、家は鉄だけでできているわけではないからです。
構造別に、防蟻処理の必要性を深く掘り下げてみましょう。
鉄骨住宅でも防蟻処理が必要な理由

鉄骨住宅のオーナー様が最も疑問に思うのがここです。
「鉄は食べられないのに、なぜ?」
実は、鉄骨住宅であっても、内装の下地や建具には多くの木材が使われています。
例えば、フローリングを支える床下地、壁の巾木(はばき)、玄関の上がり框(かまち)、和室の畳寄せなどです。
シロアリは、コンクリートのわずかな隙間や配管の周りから侵入し、鉄骨をよじ登って、これらの木部を食い荒らします。
鉄の柱は無事でも、床がフカフカになったり、壁の下地がボロボロになったりするリスクは十分にあるのです。
実際に、鉄骨メーカーの家でも、玄関周りやお風呂場周りからシロアリ被害に遭ったという事例は少なくありません。
「鉄骨だから安心」というのは、あくまで「倒壊のリスクが低い」という意味であって、「シロアリ被害に遭わない」という意味ではないのです。
シャーウッド(木造)のリスクと対策
一方、木造住宅であるシャーウッドの場合は、言うまでもなく防蟻処理は必須です。
積水ハウスのシャーウッドは、集成材などの高品質な木材を使用し、基礎パッキン工法などで通気性を高めていますが、それでも木造であることに変わりはありません。
特にシャーウッドの場合、構造体そのものが木材であるため、万が一被害に遭った場合のダメージは鉄骨よりも深刻になりがちです。
シャーウッドにお住まいの方は、費用対効果を計算するまでもなく、防蟻処理は「家の寿命を守るための義務」だと捉えるべきでしょう。
シロアリ被害に遭いやすい家の特徴

構造に関わらず、シロアリ被害に遭いやすい環境というものがあります。
もしあなたのお宅が以下の条件に当てはまるなら、防蟻処理の優先度はさらに高くなります。
- 家の周囲に廃材やダンボールを放置している
- 庭に切り株や枕木がある
- 床下の通気性が悪く、湿気がこもりやすい
- 近隣でシロアリ駆除を行った家がある(逃げてくる可能性があります)
シロアリは、湿気と木材の匂いを敏感に察知します。
積水ハウスの基礎はしっかりしていますが、庭や周辺環境からの侵入リスクまでは完全に防げません。
日頃から家の周りを点検し、シロアリを寄せ付けない環境づくりをすることも、大切なメンテナンスの一つです。
積水ハウスの防蟻処理は他社で?保証のリスク
- 他社業者の費用相場と積水ハウスとの差額
- 他社施工で構造躯体保証が打ち切られる罠
- コスト削減と長期保証のどちらを取るべきか
「積水ハウスの見積もりが高いのは分かった。じゃあ、自分で安い業者を探して頼めばいいんじゃない?」
そう考えるのは、賢い消費者として当然の発想です。
しかし、積水ハウスの場合、ここには非常に大きな「落とし穴」が待っています。
この章の内容が、今回の記事で最もお伝えしたい核心部分です。
他社業者の費用相場と積水ハウスとの差額

まず、地域のシロアリ駆除業者や、ホームセンターなどで依頼した場合の費用を見てみましょう。
一般的な相場は以下の通りです。
- 一般業者:8万円〜12万円程度(30坪)
- 積水ハウス:15万円〜20万円程度(30坪)
その差額は、約5万円から10万円。
決して小さくない金額です。
「同じ薬を使って、同じように床下に潜るなら、安い方がいいに決まっている」
そう思うのも無理はありません。
他社施工で構造躯体保証が打ち切られる罠
しかし、ここで思い出していただきたいのが、第1章でお話しした「保証延長のルール」です。
積水ハウスの規定では、「指定工事店以外での施工」は、保証延長の対象外とみなされます。
つまり、他社で防蟻処理を行った瞬間、その証明書を積水ハウスに見せたとしても、「あ、そうですか。では当社の保証はこれで終了となります」と言われてしまうのです。
これが最大の「罠」です。
目先の数万円を節約した代償として、もし将来、巨大地震で基礎にヒビが入ったり、雨漏りで壁が腐ったりしても、積水ハウスには一切責任を問えなくなります。
「それでもいい、自分は安さを取る」と割り切れるなら構いません。
しかし、「大手ハウスメーカーの安心感」を買うために高い建築費を払ったのであれば、ここで保証を手放すのは、これまでの投資を無駄にする行為とも言えるのではないでしょうか。
コスト削減と長期保証のどちらを取るべきか

結局のところ、これは「保険」の選択と同じです。
「何かあった時のために、高い掛け金を払ってでも手厚い保証(積水ハウス施工)を残す」か。
「確率は低いと割り切って、掛け金を安く済ませる(他社施工)」か。
私の個人的な見解としては、築10年、20年という段階であれば、まだ積水ハウスで施工することをおすすめします。
家はまだ資産価値が高く、何かあった時の損害が大きいからです。
逆に、築30年を超えて、建物の価値が償却され、リフォームなども視野に入ってくる時期であれば、他社施工に切り替えてコストダウンを図るのも一つの賢い戦略と言えるでしょう。
重要なのは、安易に価格だけで飛びつかず、「保証がなくなる」というリスクを正しく理解した上で決断することです。
積水ハウスの防蟻処理に関するまとめ
ここまで、積水ハウスの防蟻処理について、費用の実態から保証の仕組み、そして他社施工のリスクまでを深掘りしてきました。
私自身、リサーチャーとして様々な情報を集める中で、「積水ハウスは高い」という声の裏には、「それだけの保証体制を維持するためのコスト」が含まれていることを改めて実感しました。
15万円や20万円という金額は、家計にとって決して軽くはありません。
しかし、それは単なる「虫除け代」ではなく、「今後10年間の家の安全をメーカーに約束させるための契約金」でもあります。
もし、あなたが「積水ハウスというブランド」に信頼を置いて家を建てたのであれば、その信頼関係を継続するために必要な経費と捉えるのが、最も納得のいく考え方かもしれません。
一方で、どうしても予算が厳しい場合や、家の使用状況が変わった場合には、リスクを承知の上で他社を選ぶという選択肢もゼロではありません。
大切なのは、営業担当者の言葉を鵜呑みにするだけでなく、この記事で紹介したような「メリットとデメリット」を天秤にかけ、あなた自身の価値観で決断することです。
家は、建てて終わりではありません。
長く快適に住み続けるために、この10年目の決断が、あなたの家にとって最良の選択となることを願っています。
- 積水ハウスの防蟻処理は10年ごとの更新が必要
- 費用相場は30坪で約15万円から20万円前後
- 坪単価にすると約5000円から8000円が目安
- バルコニー防水工事とセットで提案されることが多い
- 鉄骨住宅でも内装下地に木材があるため対策は必須
- シャーウッドは構造を守るために絶対に欠かせない
- 防蟻処理を受けないと構造躯体保証が打ち切られる
- 他社で安く施工しても積水ハウスの保証延長はできない
- 他社相場との差額は5万円から10万円程度
- 差額は長期保証を維持するための保険料と考えるべき
- 築浅のうちはメーカー施工で保証を継続するのが無難
- 築30年以降なら他社施工でコストダウンも選択肢
- シロアリ被害は湿気や庭の環境にも左右される
- 見積もりが出たら内訳をしっかり確認することが大切
- 最終的には安心とコストのバランスで判断しよう