
注文住宅を計画している方にとって、契約後の予算管理はとても重要な課題です。
契約時に安心していた見積もりでも、後から発生する追加費用により予算オーバーとなってしまうケースが少なくありません。
その結果、新築で予算オーバーして払えない事態に陥ることもあります。
この記事では、注文住宅で予算オーバーする平均額や、予算を決める際に収入の何%を目安にするべきかなど、具体的な指標を交えて解説します。
また、契約後に発生しやすい追加費用の内訳や、減額できる項目についても詳しく紹介しています。
予算オーバーを防ぐためには、契約前からしっかりと情報を集めることが大切です。
複数の会社から見積もりを取り、価格や内容を比較することも有効な手段となります。
これから注文住宅を検討する方が後悔しないよう、予算計画と向き合うための正しい知識をお伝えしていきます。
- ➤ 契約後に発生する追加費用の種類がわかる
- ➤ 注文住宅で予算オーバーする主な原因が理解できる
- ➤ 予算オーバーした際のリスクや影響がわかる
- ➤ 平均的な予算オーバーの金額を知ることができる
- ➤ 注文住宅にかける適切な予算の目安がわかる
- ➤ 一括見積もりでコストを抑える方法がわかる
- ➤ 契約後でも減額できる項目とその対策がわかる
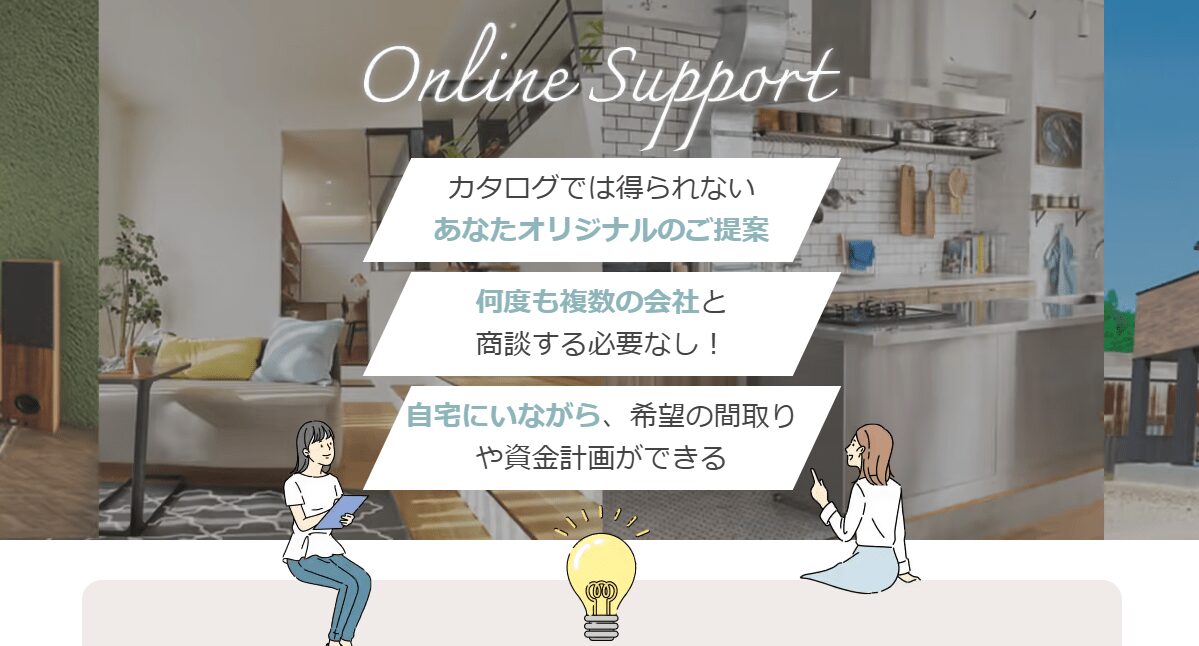
| 【タウンライフ❖家づくり】 | |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 見積り | あり |
| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |
| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |
| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |
「タウンライフ家づくり」は、サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から提案を受けることができるサービスです。
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。
大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。
注文住宅の契約後に予算オーバーが起きる理由とは
- ➤ 契約後に発生する追加費用の正体とは
- ➤ 新築で予算オーバーした場合に払えないとどうなる?
- ➤ 注文住宅で予算オーバーする平均額はいくら?
- ➤ 注文住宅にかける予算は収入の何%が目安?
契約後に発生する追加費用の正体とは

注文住宅を契約する際、多くの人は営業担当者から提示された「見積書の総額」に安心してしまいます。
しかし、その金額がすべてではなく、あくまでも「基本的な本体工事費用」であるケースがほとんどです。
実際には契約後に追加で発生する費用が数多く存在し、その内容と金額を正確に把握しておかないと、家づくりが進むにつれて驚くほどの出費が重なり、最終的に予算オーバーになってしまうという事態に陥ります。
まず、多くの人が見落としがちな項目が「外構工事費」です。
家の外側、つまり駐車場や玄関アプローチ、フェンス、庭づくりなどにかかる費用は、基本の見積もりには含まれていないことが多く、平均で100万円〜200万円程度の追加費用が発生します。
次に「付帯設備費」です。
これは照明やカーテン、エアコンなどの生活に必要な設備ですが、これらも別途購入や設置が必要な場合があり、結果として想定外の出費になります。
また、「地盤改良工事」は土地の地盤調査後に必要となることがあり、特に軟弱地盤の場合は50万円〜100万円以上かかることもあります。
この費用は調査後に急に提示されるため、精神的にも金銭的にも大きな負担になります。
さらに「設計変更による追加工事費」も無視できません。
建築中に「やっぱり収納を増やしたい」「窓を大きくしたい」といった要望が出てくることがありますが、こうした変更には当然追加費用がかかります。
また、仮住まいの家賃や引っ越し代、住宅ローン事務手数料、火災保険料、登記費用といった「諸経費」も、契約時には具体的に説明されないことが多く、これらを合計すると数十万円〜百万円以上になることもあります。
加えて、住宅ローンを組む際の金利の変動や、審査のタイミングによる費用増加など、外的要因による出費も無視できません。
このように、契約後に発生する費用には多くの種類があり、しかもその合計金額は予想を超えることが珍しくないのです。
だからこそ、契約前に「本体価格に何が含まれていて、何が別途必要になるのか」を一つひとつ確認することが重要です。
また、できるだけ多くのハウスメーカーや工務店から見積もりを取り、費用の内訳を比較することが、無駄な出費を抑える大きな鍵になります。
特に、無料で複数の有名ハウスメーカーからプランと見積もりを一括で請求できる「タウンライフ家づくり」のようなサービスを活用すれば、自分たちの条件に合ったプランを効率よく比較できます。
こうしたサービスは、不要なオプションや不透明な追加費用を見極めるためにも有効で、結果的に数十万円〜数百万円の節約につながる可能性も高いのです。
住宅購入は人生で最も高額な買い物です。
契約後に慌てることがないよう、早い段階で情報収集を始め、見積もりの比較と内訳確認を徹底することが、後悔しない家づくりへの第一歩と言えるでしょう。
新築で予算オーバーした場合に払えないとどうなる?
新築住宅の建築において予算オーバーが発生し、それに伴い支払いが困難になると、思っている以上に大きな問題に発展する可能性があります。
まず最も大きな影響は、住宅ローンの審査が通らなくなることです。
住宅ローンは金融機関が申込者の返済能力を総合的に判断したうえで貸し出されるものであり、建築費用が当初予定より高くなりすぎた場合には、借入希望額が年収や信用状況に見合わないと判断されてしまい、融資が否決される恐れがあります。
また、すでに住宅ローンの審査を通過していたとしても、予算オーバーによって金額変更が必要になった場合、再審査が必要となるケースもあります。
再審査の結果、融資額が満たない場合は、自身で差額を用意する必要がありますが、これができなければ最悪の場合は契約自体を白紙に戻すことになりかねません。
次に考えられるリスクとしては、建築途中での工事ストップです。
建築会社やハウスメーカーは、契約時に定めたスケジュールと金額に基づいて作業を進めますが、施主が途中で支払い不能となった場合は、工事が一時中断されることがあります。
この間に発生する諸費用や延期に伴うコストは、すべて施主側の負担となり、さらに経済的な圧迫を生むことになります。
また、契約上の違約金が発生する可能性も高く、元に戻すことが困難な状態となります。
さらに、工事が遅れることで引っ越しや仮住まいの手配に支障をきたし、家族の生活基盤にも悪影響が及ぶ可能性があります。
精神的なストレスも相当なものであり、せっかくの夢のマイホームが「後悔の象徴」になってしまうことも少なくありません。
このように、予算オーバーにより「払えない」という状況は、住宅取得の根幹を揺るがす非常に重大な事態を引き起こすことになります。
そのため、最初から「予算をオーバーしない家づくり」を意識し、見積もりの時点で十分な比較・検討を行うことが極めて重要です。
特に一括見積もりサービスを活用すれば、複数のハウスメーカーや工務店から無料でプランと金額を比較できるため、予算に見合った提案を見つけやすくなります。
「タウンライフ家づくり」のようなサービスは、見積もりの透明性を高め、追加費用の有無も明確に示してくれるため、予算管理の強い味方になります。
夢の注文住宅を現実にするには、「払えなくなるリスク」を避ける慎重な準備と情報収集が必要不可欠なのです。
注文住宅で予算オーバーする平均額はいくら?

注文住宅の建築では、ほとんどの家庭が当初の予算よりオーバーしてしまう傾向にあります。
その予算オーバーの平均額は、一般的に100万円〜300万円ほどと言われています。
もちろんこの金額には幅がありますが、建築に必要な工事費用や設備のグレードアップ、土地造成費など、最初に想定していなかった項目が後から追加されることが大きな要因となっています。
また、見積もり時点では省かれていた外構費や照明、カーテン、エアコンといった付帯工事・備品の費用も、最終的に加算されていくことが多いです。
そのため「本体工事費は予算内だったのに、トータルで見たら大幅にオーバーしていた」というケースが頻繁に見られます。
住宅メーカーによっては、契約後にオプションの追加提案が続き、最終的には何百万円も上乗せされていたという事例も少なくありません。
さらに、注文住宅は施主のこだわりが強く反映される傾向にあり、キッチンやお風呂、床材など「せっかく建てるなら良いものを」と思い始めることで、当初の予定より大幅に高額になるパターンもよくあります。
このような経緯から、結果的に数十万円から数百万円の予算オーバーとなる人が多いのです。
この事実を知っておくことで、あらかじめオーバーを想定した余裕のある資金計画を立てることができ、後悔のない家づくりにつながります。
そのためにも、複数社からの一括見積もりを活用し、総費用を比較しながら、正確な予算感を把握することが非常に重要です。
注文住宅にかける予算は収入の何%が目安?
注文住宅の予算を考えるうえで、収入とのバランスは非常に重要なポイントです。
一般的には、年収の5倍〜7倍が住宅ローンの借入額の目安とされており、住宅にかける総予算としては年収の25%〜30%程度が安全ラインと言われています。
たとえば、年収500万円の世帯であれば、年間の住宅ローン返済額が125万円〜150万円以内に収まるように計画するのが望ましいとされています。
月額に換算すると、約10万円〜12万円程度の支払いであれば、家計への負担が過度にならず、生活に余裕を持たせながら住宅を維持していくことができます。
ただし、これはあくまで一つの目安であり、家族構成やライフスタイル、教育費や老後資金などの他の支出も考慮したうえで計算することが大切です。
また、住宅ローンの返済以外にも固定資産税や維持管理費など、住み始めてから発生する費用もあるため、それらも含めた総合的な予算設計が求められます。
無理なローンを組んでしまうと、生活が苦しくなったり、教育や老後資金に支障が出たりするため、「借りられる金額」ではなく「無理なく返せる金額」を基準に考えるべきです。
そのためにも、住宅のプランや見積もりは複数社に依頼して内容を比較し、最も納得できるコストバランスの取れた提案を選ぶことが、家計に優しい注文住宅づくりにつながります。

| 【タウンライフ❖家づくり】 新しい住まいのプランを一括お届けサービス | |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 見積り | あり |
| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |
| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |
| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |
全国1,170社以上(※)の注文住宅会社を自宅にいながらまとめて比較できる「タウンライフ家づくり」。
サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から選べます。
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。
大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。

注文住宅の契約後に予算オーバーを防ぐための対策
- ➤ 一括見積もりで価格の比較をする重要性
- ➤ 複数のハウスメーカーから見積もりを取るべき理由
- ➤ 「タウンライフ家づくり」で無料で一括請求する方法
- ➤ 注文住宅の契約後に減額できる項目とは
- ➤ 注文住宅の契約後に予算オーバーになるケースと対処法
一括見積もりで価格の比較をする重要性

注文住宅を建てる際に、最初に気を付けておきたいのが「見積もりの取り方」です。
一社や二社だけに見積もりを依頼して決めてしまうと、その金額が本当に妥当なのかを判断する材料がなく、結果として割高な契約をしてしまう可能性があります。
特に注文住宅では、建築会社ごとに提案内容も価格も大きく異なります。
同じ大きさ、同じ間取りの家であっても、会社によって500万円以上価格に差が出るケースもあります。
それは、建築会社ごとに仕入れルートや工法、営業コスト、ブランド戦略などが異なるためです。
例えば、A社では標準仕様となっている設備でも、B社ではオプション扱いとなり追加料金が発生することがあります。
このように、各社の見積もりを比較しなければ、自分たちにとって本当にコストパフォーマンスの良い選択ができなくなってしまいます。
一括見積もりサービスを利用すれば、複数のハウスメーカーから一度に提案を受けることができ、手間なく比較検討が可能です。
また、比較することで各社の提案の違いや費用の根拠も分かりやすくなり、自分たちの希望に最も近い会社を選ぶ判断材料になります。
そのため、注文住宅を検討する際には、必ず一括見積もりを取り入れることが非常に重要です。
複数のハウスメーカーから見積もりを取るべき理由
注文住宅を建てる際に、見積もりを一社だけから取るのは非常に危険です。
なぜなら、ハウスメーカーごとに建築費用や提案内容が大きく異なるからです。
たとえば、同じ30坪の家を建てようとした場合でも、A社では2,000万円、B社では2,500万円、C社では1,800万円というように、大きな差が出ることがあります。
この差は、使用する建材のグレード、標準仕様の内容、設計の自由度、工法、広告費などさまざまな要因によって生まれます。
つまり、1社や2社だけの見積もりで決めてしまうと、もっと安くて希望に近いプランを出してくれる会社の存在に気づかないまま、高い金額で契約してしまう恐れがあります。
また、複数の見積もりを比較することで、それぞれの会社がどのような強みや弱みを持っているのかが見えてきます。
価格だけでなく、間取りの工夫や住宅性能、アフターサービスの違いまで比較できるため、自分たちの理想の家に近づける可能性が高まります。
さらに、複数社の競争が生まれることで、値引きやサービス内容のアップグレードを引き出せる場合もあります。
一括見積もりを取ることは、家づくりのスタートラインに立つうえで、もはや必須と言っても過言ではありません。
「タウンライフ家づくり」で無料で一括請求する方法

「タウンライフ家づくり」は、複数のハウスメーカーや工務店から、無料で一括見積もりを依頼できる便利なサービスです。
まず、専用のフォームから家づくりに関する希望を入力します。
入力内容は、土地の有無や建築希望エリア、家族構成、間取りのイメージ、予算の目安などです。
これらの情報をもとに、提携している住宅会社がそれぞれの要望に合わせたプランや見積もりを作成し、送ってくれます。
資料は郵送やメールなどで届けられるため、自宅にいながら比較検討が可能です。
このサービスの大きな魅力は、全国600社以上のハウスメーカー・工務店から提案を受けられるという点です。
大手メーカーだけでなく、地元に強い工務店からも提案を受けられるため、選択肢の幅が広がります。
また、営業電話が苦手という人も、フォーム入力だけで完結するため安心して利用できます。
実際にこのサービスを使った人の多くが、「最初の見積もりよりも数百万円安くなった」「希望以上の間取りが提案された」といった声をあげています。
注文住宅で失敗しないためにも、「タウンライフ家づくり」を活用して、まずは複数社の見積もりを手に入れることが重要です。
注文住宅の契約後に減額できる項目とは
注文住宅では、契約後に予算オーバーが発覚することがあります。
その際に検討されるのが、減額調整です。
この調整は「コストダウン」や「仕様変更」とも呼ばれ、予算に収めるために行う調整作業です。
減額できる代表的な項目としては、まず「設備機器のグレード変更」があります。
キッチンやトイレ、ユニットバスなどの住宅設備は、グレードによって価格が大きく異なります。
例えば、高機能なキッチン水栓や食洗機などは便利ではありますが、グレードを下げるだけで数万円から十数万円の減額につながります。
次に「仕上げ材の見直し」も効果的です。
床材や壁紙、外壁材などの仕上げは見た目に大きく関わりますが、選択肢を変えることでコストを抑えることが可能です。
また、「造作家具や収納の簡略化」もよくある方法です。
現場で造作する収納や棚は費用がかかるため、市販の家具に置き換えるだけでも大きな削減になります。
さらに、「照明やコンセントの数の見直し」も挙げられます。
最初のプランでは過剰に設置されていることもあるため、実際の生活動線を想定しながら削減できる部分を精査すると良いでしょう。
なお、減額の際は「後で後悔しないか」をよく検討することが重要です。
生活の快適さに直結する部分まで削ってしまうと、不便を感じる原因になります。
減額はあくまでも「なくても困らない部分」「市販品で代用可能な部分」に限定するのが理想です。
プロである建築士や営業担当に相談しながら、後悔のない減額調整を行いましょう。
注文住宅の契約後に予算オーバーになるケースと対処法

注文住宅の契約後に「予算オーバー」が起きるのは決して珍しいことではありません。
この問題は、住宅計画の初期段階での見積もりが甘かったり、要望が増えたりしたことで発生します。
予算オーバーが起こる典型的なケースとしては、「追加工事費」が挙げられます。
例えば、地盤調査の結果、地盤改良が必要と判断されると、数十万円から百万円単位の費用が追加でかかる場合があります。
また、「建築確認後の仕様変更」も予算オーバーの原因になります。
契約後に間取りや内装を変更すると、設計のやり直しや資材の変更費用が発生します。
さらに、「外構工事を後回しにしていたが、思ったより費用がかかった」という例も少なくありません。
このようなケースでは、すでに着工しているため大幅な変更が難しく、結果的に泣く泣く予算を上乗せしてしまうことになります。
対処法としてまず行うべきは、「着工前の徹底的な見直し」です。
着工前であれば、仕様変更や減額調整が比較的容易であり、最終的な工事費を抑えやすくなります。
次に、「建物本体と外構を別予算で管理する」ことも有効です。
総額の中で曖昧になりやすい外構工事の予算を明確にし、プラン通りに進めることで、予算管理がしやすくなります。
また、「見積もりの内訳を細かくチェックする」ことも重要です。
見積もりの項目ごとに金額を確認し、相場と比較しながら、必要以上にコストがかかっていないかを確認しましょう。
最後に、「一括見積もりサービスを利用する」のも非常に有効な手段です。
複数の住宅会社から見積もりを取り寄せることで、相場感をつかみやすくなり、過剰な費用を避ける判断材料になります。
予算オーバーは決して他人事ではなく、誰にでも起こりうる問題です。
事前の対策と冷静な見直しで、無理のない家づくりを実現しましょう。
- ➤ 契約後に発生する追加費用の正体とは
- ➤ 新築で予算オーバーした場合に払えないとどうなる?
- ➤ 注文住宅で予算オーバーする平均額はいくら?
- ➤ 注文住宅にかける予算は収入の何%が目安?
- ➤ 一括見積もりで価格の比較をする重要性
- ➤ 複数のハウスメーカーから見積もりを取るべき理由
- ➤ 「タウンライフ家づくり」で無料で一括請求する方法
- ➤ 注文住宅の契約後に減額できる項目とは
- ➤ 注文住宅の契約後に予算オーバーになるケースと対処法
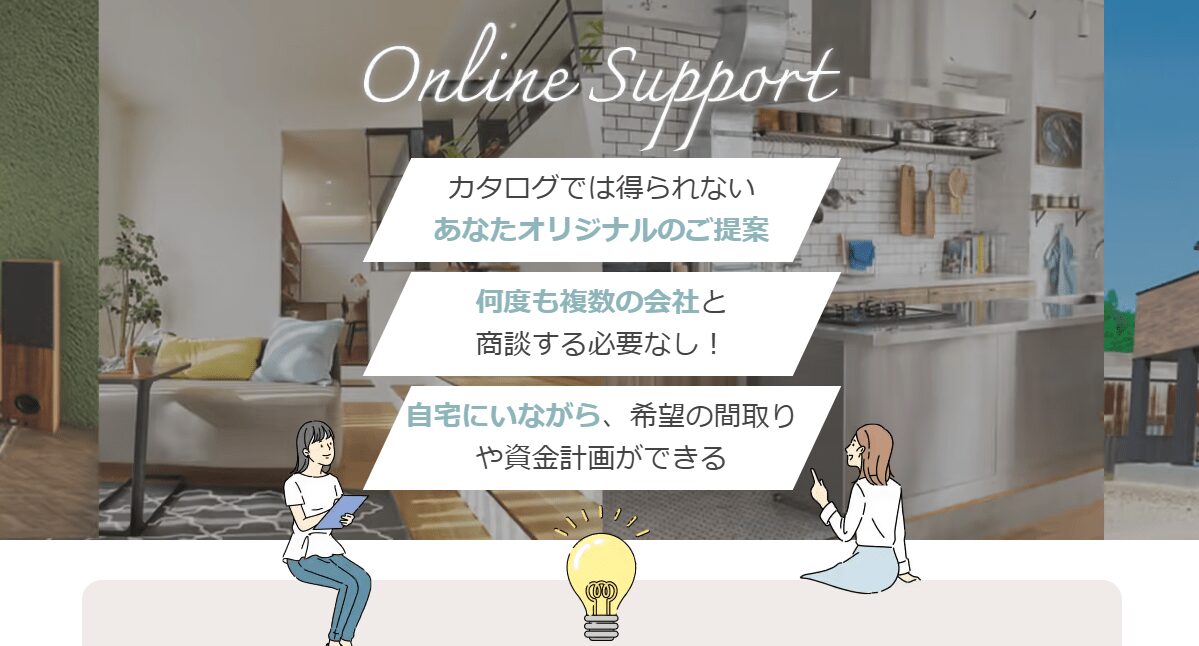
| 【タウンライフ❖家づくり】 | |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 見積り | あり |
| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |
| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |
| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |
「タウンライフ家づくり」は、サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から提案を受けることができるサービスです。
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。
大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。













